我々は死について深く考える時、死を悪のように見ることが多いのではないだろうか。それも無理もないことである。死は、誰もが経験したこのない故に、悲しみや恐怖や痛みなど全ての不幸が凝縮したような感覚を抱くことが多いからだ。
宗教では、そんな死に対する理解や意味を深めるために死後の世界の説明することで生きる価値や意味を教えてきた。仏教では極楽浄土、キリスト教では天国や地獄などがある。
しかし、日本では、1995年に起きたオウム真理教での地下鉄サリン事件から宗教に対してマイナスの感覚を抱くことがあり、神という存在を信じる人の心理が理解出来なくなり、科学主義者が増えていったように思う。
哲学の視点から死を知るということは、生命とはどのような存在なのか。人間は何のために生きているのか、死後の世界は存在するのか。神という存在を考える事なく、それらの問いを深く理解する事に繋がる。
我々は死について恐怖を抱くことが多いが、死は現に悪いものなのか。死が現に悪いものなら、不死は良いものなのかという疑問が浮かんでくるはずだ。
この文章を読み進めていくと自ずとわかるはずだが、それと同時に次の疑問を問う必要がある。
- 私の生き方は、やがて死ぬ事実にどのような影響を受けてしかるべきなのか。
- 必ず死ぬという運命に対して、私はどのような態度を取るべきなのか。
- 死は恐れることなのか。
- やがて死ぬという事実に絶望すべきなのか。
本文を読み進めていくと、「死の本質」の理解が深まることと、「死に対しての考え方」が変わることをお約束したい。
死についての考察では、イェール大学で人気の講義であったシェリーケーガン氏『DEATA』を基に、本文を進めたく思っている。
書籍は、余命宣告をされた学生が命をかけて受けたいと願った講義であり、死に対しての接し方、生きる価値などを深く考えさせられるものである。
本文の最後には自殺に関する疑問にも目を向けている。命は貴重な価値があるのだから、自殺は決して理にかなわないと、多くの人たちは考えている。というわけで、最後には、自殺の合理性や道徳性を検討していきたい。
以上がこれから取り組んでいくことだ。本文から、読者の死に関しての考え方が変わることを私は望んでいる。
第1章 死は何故悪いのか

死は悪いものだと誰もが信じている。ではどうして死が悪いということがありえるのか。死が悪いとするならば、永遠に生きるのは良いことなのか。この問題は答えが難しいが、ここを詳しく検討する必要がある。
では、死は、どんなふうに悪いのか。この疑問について考える時、私の身体の死は人格を持った人間として私の存在の終わりを意味すると単純に仮定する事になる。しかし、一旦死んでしまえば、私はもう存在しない。存在しないのであれば私にとってどうして悪いことでありうるのか。
死は残された人にとって悪いのか?
まず死は残された人にとって悪いものなのかを考えていきたい。
つまり、死んだ人にとって悪くないが、それまで私を愛していて、これから彼なしで生き続けなければならない人にとって悪い、友人や家族にとって悪いということなのか。誰かが死ぬということは、私達はその人と交流し続ける機会を失うことになる。
それは、その人と話したり、一緒にいる映画を見たり、笑ったりすることができないということだ。それが死の最悪の点かもしれないが死んだら本人がどのような目に遭うかが問題ではない。死は本人にとって悪くないのだから。
ここで考えを謳いあげた詩を紹介しよう。ドイツの詩人フリードリヒ・ゴットリープ・クロプシュトックによる「別離」と呼ばれる詩だ。
あなたはその亡骸が私たちの前に運ばれた時、ひどく厳粛になった。
あなたは死を恐れているのか?「いや、それは恐れてはいない」
それなら、何を恐れているのか?「死ぬことだ」
私はそれすら恐れていない。「それでは何も恐れていないのか?」
いや、恐れている。私は恐れているの。「何を、それなら一体何を?」
友達と別れることを。
それも、私が別れるばかりではなく、彼らが別れることも。
だからこそ私は、あなたよりもなおいっそう、
魂のより深くで、厳粛になった。
あの亡骸が
私たちの前に運ばれてきたときに。
クロプシュトックによれば、死に関して決定的に悪いのは、友達を失う事のようだ。彼らが死ぬと彼らを失う。そして先ほども述べたとおり、これは死にまつわる悪い点であり、それをみくびるつもりはない。
だがそれは、死のどこが悪いかに関してはその核心があるとは思えない。死が悪い理由について中心的事実がない。
もし、死が悪いのは主に何のせいかを理解したければ、別離が悪いと言うことや残された人に悪いと言う事に的を絞るわけにはいかないように思える。
私たちは、死ぬ人にとって死が悪いというのがどうして真実でありうるのかを考えなければならない。本人にとって悪いというのが、死が悪いことである主な理由であり、それこそが注目しなければならないことだ。
これから歩む人生の機会を失うから?
では、人生の今後の機会を奪うから悪いという考え方はどうであろうか。非存在は、今後の人生が提供してくれるだろう様々な良い事をもう経験したり楽しんだりできないからだ。
この説明は、今日では死の害悪或いは悪さを説明する剥奪説として知られている。
私が思うに、人生における良いことを死が剥奪する点であると主張する説は、正しいと思えるが「生まれる前」と「死んだ後」の時間は、同じ価値を持つのだろうか。
死は人生を失う事を意味するが、誕生前の期限は、私はまだ生きてはいないけれど、人生を失ってはいない。だから、死後の期間の方が悪いのは、死には喪失が伴うのに対して、誕生前は喪失を伴わない事実がある。というわけでこの主張は死後の人生の剥奪だからこそ悪いと感じるのだ。
剥奪説は全体として妥当ではあるが、様々な異論の中で剥奪説は受け入れるべきではないと結論した人々も存在し、更に驚くべき主張をしている人々だっている。古代ギリシアの哲学者エピクロスの文章には、人々を2000年にわたって頭を悩ませてきた。これがエピクロスの文章だ。
あらゆる災難のうちでも最も恐ろしい死は、私たちにとって取るに足らないものなのだ。なぜなら、私たちが存在している限り、死は私たちとともにないからだ。だが、死が訪れたときには、今度は私がが存在しなくなる。ならば、死は生者にも死者にも重要ではない。前者にとっては死は存在しないし、後者はもはや存在しないのだから。
私達はこの主張にどう応じるのか自問する必要がある。この主張は死が「悪いこと」になるタイミングを考える必要がある。剥奪説によれば、死が悪いのは、人が死んだとき、人生における良い事を剥奪されるからだという。
では、死はいつ本人にとって悪いのか?おそらく、人生における良い事を剥奪されている間だろう。
それなら、人生における良い事を剥奪されているのはいつであろうか。死んでいる時だ。だから、エピクロスにこう言えさえすれば良いのかもしれない。
「あなたは正しかったんですよ、エピクロス。あらゆる事実は時点を定めなくてはなりません。けれど私達は、死がいつ悪いか特定することができます。死は、本人が死んでいるとき、その人にとって悪いのです。なぜなら、そのときその人は、依然として生きてさえいれば経験できていたであろう、人生における良い事を剥奪されている、経験していないからです」
これは、エピクロスの主張に対する返答として成り立っているのではないだろうか。剥奪説について肝心なのは、人は存在する必要さえ無い点だ。存在しなければ、なにかを剥奪されることが確実になということだ。
この剥奪説に関して、シェリーケーガン氏は、
死にまつわる最悪な点を実際にはっきりと捉えているように見える。
と述べている以上、死が何故悪いことでありうるのかについてはまだ完全な答えが得られてないにしろ、剥奪説は最も重視する考え方であるように思える。
第2章 不死について考える
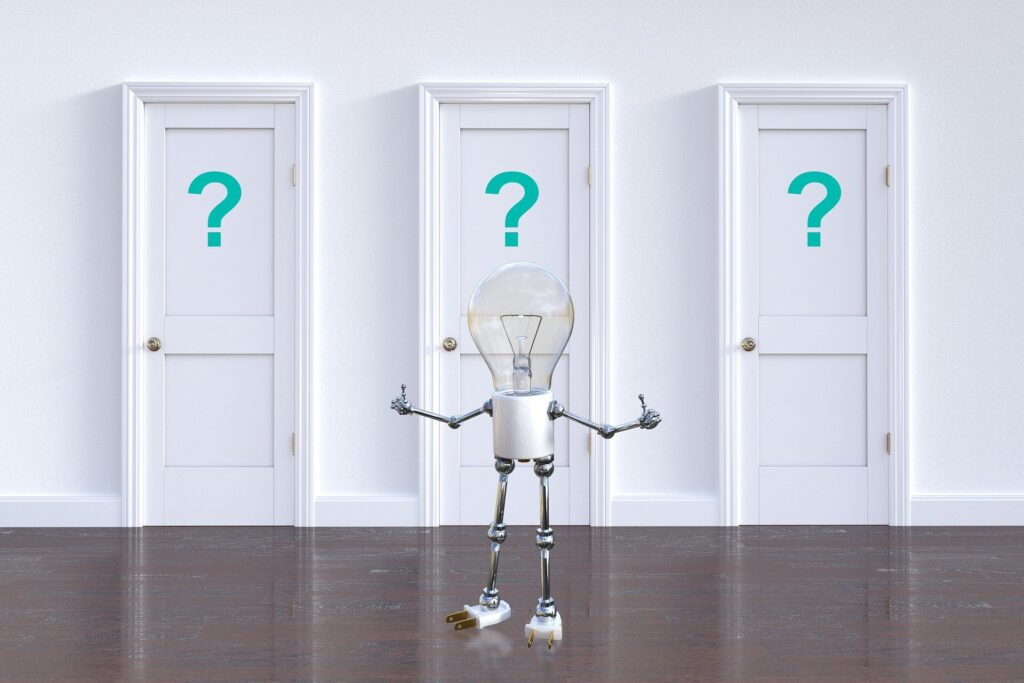
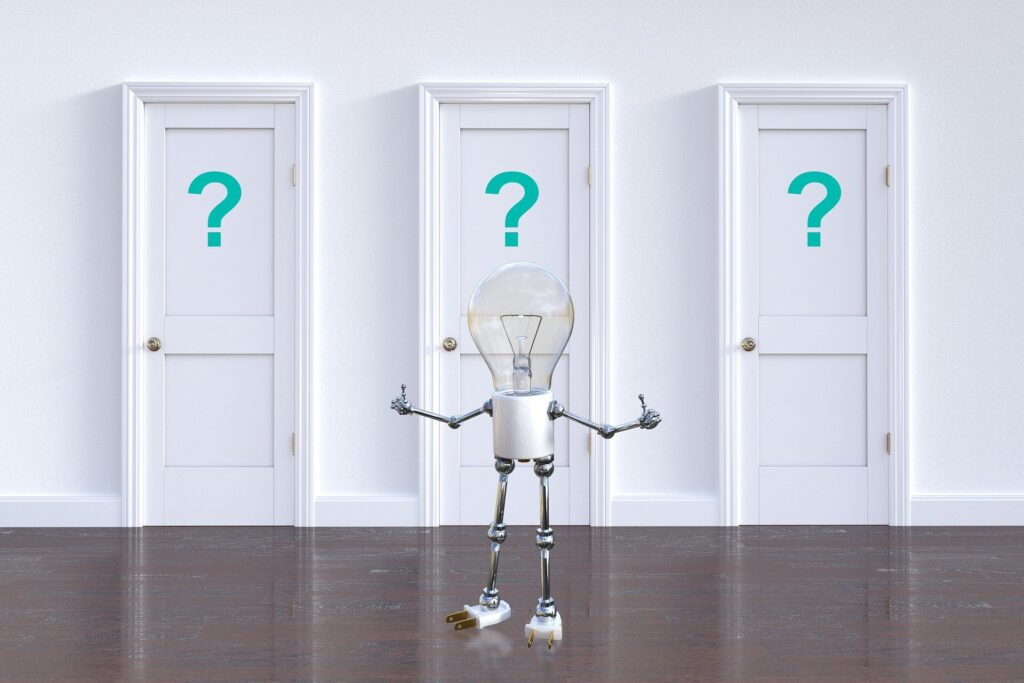
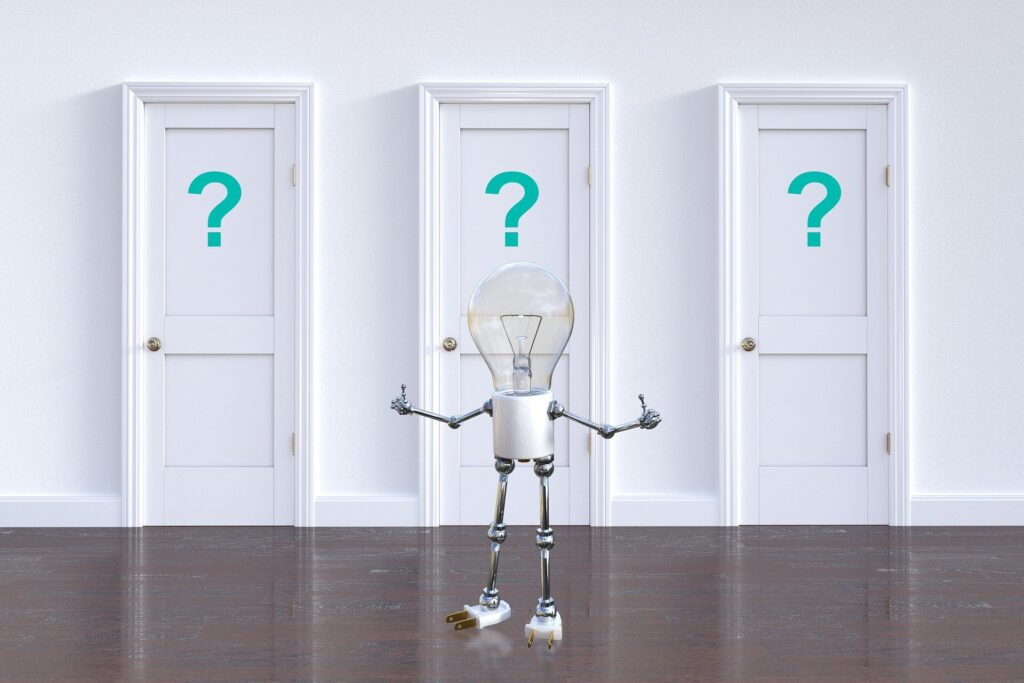
死は人生における良い事を剥奪するから悪いのであれば、最も望ましいのは永遠に生きる事なのだろうか。
死が悪いのはこの剥奪のせいであるという説を受け容れれば、不死でいる方が望ましいということになるのだろうか。では、長く生きるほど、人生は良くなるのか考えていきたい。
例えば、悲惨な事故で10歳で命を落とすとしたら、40歳まで生きられた方が良かったのだろうか。或いは、それ以上生きた方が、本人にとって幸せだったのか。しかし、人は歳を取るだけでなく、身体が弱り、不自由になっていく事実がある。
不死を手にすれば、その分不快なことが増えていき、凄まじい勢いで老化が進む。そして頭の働きが失われて、絶えず痛みに襲われる。モンテーニュは死についてこのように述べている。
死はじつは恵みだ。老化になった私たちが見舞われる痛みや苦しみ、惨めさに終止符を打ってくれるからだ。
確かにこの主張は正しいと思えるが不死にもこの反対の主張も許されるのではないか。つまり、毎日が楽しく健康な状態で永遠に生きるということだ。永遠の命を手にしても、必ず健康でいられなければ地獄を見るわけだ。
では、永遠に生き、健康でいられるとしよう。そしたら、どんな種類の人生を想像すれば、その人生に価値が出てくるだろう。つまり、100年後1000年後の話ではなく、永遠になにをして生きるかだ。
こういう生き方なら永遠にそれだけを続けたいというものを、皆さんは描き出せるだろうか。
イギリスの哲学者バーナード・ウィリアムズは、どんな種類の人生も永遠に望ましく魅力的なものにはならないだろうと主張している。この点は、シェリーケーガン氏も同意している。考えても見てほしい。
あなたはフランス料理が好きだとしよう。しかし、毎日、毎日、何千年も何万年も何億年も食べるという見通しは、魅力的には感じられない。私は、読書やゲームも好きなんだがそれを何億年もやり続けるということは、
むしろ、悪夢のようにも思える。一つのことを一貫してやり続けるのではなく、日にちを変えて別のことをやるにしても、永遠にするとは魅力に感じない。
ではただ快楽を得続ける状況に置かれたらどうであろうか。
科学者がラットを連れてきて脳に電極をつけ、電流を流したときにラットの脳内の快楽中核を刺激して、一瞬ラットに快楽を与えるという実験をやった。その電極から伸びる電線をレバーにつなぎ、レバーを押して
快楽を得る方法をラットに教えたとする。
すると、ラットはどうするか?
ラットは、食べる事も他のことに全く興味を示さなくなり、ひたすらレバーを押し続け快楽を自ら与え続ける。皆さんも快楽の爆発が永遠に続くところを想像してほしい。
それ以外に望むものはあるだろうか。しかし、私自身はこれを魅力的にも思わないし、シェリーケーガン氏も同じように言っている。
人間には、自らの経験を振り返り、その経験を評価し自己成長を求めたりする。私は、人生とはただ快楽のためだけにあるのかと疑問に思う。人間とはラットのような境遇以上のものがあるということができるだろう。永遠とはラットには良いかもしれないが、人間には良くないと私は感じる。
これまで不死を考えた時に、最善の「生」は不死ではないであろう。
しかし、ここで考えられる最善の「生」は満足するまで、人生が提供しうる良い事を全て手に入れるまで、生きられるのが良いだろうというものだ。
剥奪説は私達がいずれ死ぬのは悪い事だとしてはいないというが、この説の最善の解釈である事だ。
不死は、望ましくなく、果てしない悪夢だろうと考えるのが正しければ、いずれ私達が死ぬのは実は良いことで、何故なら、私達が不死に直面しなくても済む事を保証するからだ。
最後に、不死というテーマを離れる前に、不死についての名言を紹介したい。彼女は永遠に生きたいですか?と聞かれこう答えた。
永遠に生きたくはありません。
私たちは永遠に生きるべきではないからです。
もし私たちが永遠に生きるはずだとしたら、永遠に生きることでしょう。
でも、私たちは永遠に生きられません。
だから私は、永遠には生きたくないのです。
この言葉こそ我々は大切にしないといけないのではないか。
第3章 死が教える「人生の価値」の測り方



これまでは、次のように主張してきた。死が悪いものだと誰もが思う理由は、生きていれば良いことが経験出来るのに、死によってその経験を剥奪されてしまうということだ。
しかし、死ななかったら経験できたはずの事を足し合わせたらプラスではなくマイナスだったとしたら、死は良いことになる。つまり、人生に良い経験を剥奪するなら、死は悪いが、人生の悪い経験を剥奪してくれるなら、死は良いことになるということだ。
これらを述べるにあたって原則として人生の質を考える必要がある。すなわち自分がどれほど良い境遇、恵まれた環境にいるかがこの種の全体的な判断を下すことのできるという前提だ。
では、人生の良し悪しはなにによって決まるかこの難解なテーマを議論してみよう。
人生の質をどう評価する問いに対して、道徳的に問うのではなく、何が本人にとって人生を良くしているのかを考えるのだ。では、皆さんの人生で手に入れたい経験をしたりする価値は何だろうか。思いつくままあげてみよう。
仕事に持つ価値、あらゆる快感、お金、アイスクリーム、旅行、ゲームがある。
では、人生にとってマイナスなことは何があるのか。
視力を失う、強盗に遭う、失業、戦争、病気、精神的苦痛、痛みなどがあるだろう。
まず、間接的に良いものと本質的に良いものがあり、それらが導く結果に価値があるものとないものがある。
例えば仕事を考えてほしい。仕事は価値があるから皆がやるのだが何故価値があるのか?それは、お金が手に入るからだ。そのお金に価値があるのだが、何故お金に価値があるのか?なんと言っても好きな事ができるからだ。私にとってはアイスクリームを食べれるからだ。では何故アイスクリームには価値があるのか?アイスクリームを食べると快感が得られるからだ。ここまでは問題ないだろう。では次に何故快感には価値があるのか?ここで答えの質が変わる。つまり、その快感自体に価値があるのだ。
他のものは手段として価値があるだけで、突き詰めれば快感に至るための手段であったのだ。手段として有益なものは、間接的には価値がある。
では快感の反対はなんであろう。それが痛みである。
何故病気が悪いのかと問われると、快感を奪われ痛みを伴うからだ。
考えると、身近にある良いものや悪いものの大半が良かったり悪かったりするのは、それらの間接的な効果の結果にほかならないという事だ。快感と痛みは、本質的に人生の価値を上げたり下げたりする唯一のものではないかもしれないが、その類いのものの一つであることは確かだ。
実際に「快楽主義」と呼ばれる人は、本質的に価値のある唯一のものは快感であり、本質的に悪い唯一のものは痛みだと主張するのだ。それは、境遇の良し悪しの本質に関する非常に単純な説を提供してくれる。
良い境遇にあるのは快感を経験し、痛みの体験を下げたり最小限にしたりすることだ。そう考えるのが快楽主義である。
快楽主義者は単純でスッキリとした答えを示している。人生がもたらすものに手に入れる価値があるかどうかを判断する場合、大雑把に言えば、「今後やってくる時間を全て足して、そこから悪い時間を全て引いた答えがプラスになるかマイナスになるか」を見れば良い。
快感を全部足して、そこから痛みを全部差し引けば良い。もし答えがプラスなら、今後の人生は生きる甲斐がある。プラスへの傾きが増していけばいくほど、人生はますます生きる価値が高まる。
だが、もし答えがマイナスなら、将来に総じて快感が痛みを凌ぐ。その場合は悲しいことに死んだほうがましだと考える。これが快楽主義者の言い分だ。
このようなプラス(快感)とマイナス(痛み)の計算から人生の価値を測る快楽主義者に対してシェリーケーガン氏はこう述べている。
快感は良いものではなく痛みは悪いものではないと、私が考えているわけでは断じてない。快楽主義が間違っているのは、本質的に重要となるのは快感と痛みだけであるとしている点だ。・・・(中略)・・・人生には快感ばかりで痛みがないことより、もっと大切なことがあるからだ。というか私にはそう思えるのだ。
むろん快楽主義者にしても、レバーを押して得られる快感が、この世に存在する唯一の快感ではないことを指摘できる。芸術に触れたり、美しい夕日を見たり、夢中になるほど面白い本を読んだり、驚くべき発見をしたりする経験から得られる快感もある。みなさんはどう思うか知らないが、少なくともあのレバー装置を想像したとき、それから得られるのは単純で単調な快感のように私には思える。
だから実際には、最高級の快感、つまり友情を育み、語り合い、睦み合い、愛し合うといった、人間が真に絶望する快感を私たちに与えるという目的を遂げることはないであろう。
では快楽と痛みを考える以外に、価値ある人生とはどのような人生なのか。ここを明らかに必要がある。
この世には、快楽主義者の他にも、あらゆる状況で総計はいつもプラスだと考える楽観主義者や人生には良いことよりも悪いことの方が多いと主張する悲観的主義者なども存在する。
この楽観主義者と悲観主義者の間に、どちらでもない穏健派がいる。
これら三つの立場が全て共有している事は、生きている価値は、人生の中身と呼べるものを全て合計して求められているということだ。痛みと快感、実績と失敗などを合計し、総計して求め価値を決める。
つまり、人生は器に過ぎず、様々な良し悪しの出来事により器を満たし価値を測るという事だ。生きるという事は全く価値のないという点だ。これをシェリーケーガン氏は「ニュートラルな器説」と呼んでいる。
だが、人生の中身の価値について考えていることに加えて、人生そのものに送る価値があると主張している人もいる。
人生の良し悪しではなく、生きていること自体の恩恵というものがある。そう考える人は、現に生きているという、ただそれだけの事実が人生にさらなる価値を与えると主張する。それを、シェリ―ケーガン氏は「価値ある器説」と呼んでいる。
価値ある器説は、二つのタイプに分かれている。一つ目が、生きている事自体はいい事であっても、人生の中身が苦痛の連続で、あまりにも酷ければ、それが生きていることの価値を凌ぎ、総計がマイナスになるという「控えめな器説」がある。
ここで注目するのは、生きているプラスの価値が、人生の不運が生きている価値を失わせるという点だ。
2つ目のタイプは、生きているそのものには信じられないほど価値があり、中身がどれほど身の毛がよだつ悲惨な人生でも、総計はいつもプラスになると考えている人であり、それを「夢のような器説」と呼んでいる。
ここでまた何故死が悪いか問い直してみよう。
1章で述べた結論は剥奪説であり、それは今死ぬことで、これから送るはずだった良いことが全て剥奪されるからだ。だが、死に剥奪されるのが、本人にとって悪かったであろう未来であれば、死は良いことになる。
今何がわかるかと言えば、自分が直面するのはどちらの人生になるかを知りたければ、ニュートラルな器と控えめな器説と夢のような器説のどれを受け入れるかを決めなければならないということだ。
もしニュートラルな器説を支持するなら、人生の一時期が経験する価値があるものとなるなら、来週、来年、あるいは今後の10年生きる代わりに今死んだら、死は悪いものとなる。
だが、この後がマイナスであれば、今死んだ方がましだと考える。
控えめな器説を支持するなら、人生における次の一時期の中身を見てみなくてはならないには同意するが、同時に特別なポイントを総計に加算するのを忘れてはならないと主張する。
人生が多少悪くても、生きていること自体に価値があるのなら、本人にとって今死ぬのは悪い事になる。しかし、あまりにも悲惨な人生で生きる価値を凌いだ場合は死は良いことになる。
それとは対照的に、夢のような器説の支持者は、どれだけ悲惨で悲しい人生でも、常に長く生きる方が価値があるという事になり、死は常に悪い事になる。つまり、不死がどれだけつまらない人生になってもかまいはしない。何故なら生きている事が最高の価値なのだからと主張するからだ。
しかし、シェリーケーガン氏は、この夢のような器説は妥当だとは思っていないということだ。何故なら、不死の人生の中身が最終的にどれほど悪くなるかという疑問をあっさり無視できるとは思っていない。
しかし、控えめな器説を受け入れる気になっている時にさえ、生きていること自体がどれほどプラスの価値を持っていたとしても、いずれ不死の人生のマイナスの中身がそれを凌ぐだろうという気持ちに傾いているということだ。つまり、シェリーケーガン氏は、不死はいずれ、私たちの誰にとっても、全体として悪いものになるだろうと伝えているのだ。だからこそ、いずれ死ぬ事は実は良い事だと主張したいのである。
しかし、それでも不死を批判する考え方は、死はあまりにも早く訪れすぎるという考え方と矛盾してしまう。あと10年生きられたほうが良かったかもしれない時に、私たちは死ぬかもしれない。
そこで楽観主義者と悲観主義者、そして穏健派との区別を思い出す必要になる。
万が一、どんな未来も良いものしかないと信じている楽観主義者の意見が正しいのなら、実際に送っている人生ではあまりにも早く訪れすぎる意見に共感できる。しかし、悲観主義者は、死は誰にとってもけっして一瞬たりとも早く訪れ過ぎることはないという。人生の一時期は常に得る価値がなく悪いと思っているからだ。
その中でシェリーケーガン氏は穏健派に共感している。皆が死は早く訪れ過ぎると主張することもわかるが、世の中には悲惨なことに、人生を送るうちに体が不自由になったり、健康が損なわれたり、痛みに苦しめられたり、生き続けてもなんも恩恵も得られないように見えるところまで至る人もいる。
そのようなケースは現に存在して、その人たちにとって死が早く訪れ過ぎるという事はないということだ。
第4章 自殺



私たちはいずれ死ぬ運命にある以上、自らの人生を終わらせる道も開かれている。自殺は、自分の生きる長さをコントロールすることができ、その気になれば自分の人生を早めに終わらせることだって可能なのだ。そこで今回死について検討したい最後の疑問はこの二点である。
- もし自殺をするのが理にかなっている状況があるとしたら、それはどんな状況だろうか。
- もし自殺をするのが適切だという状況があるとしたら、それはどんな状況だろうか。
自殺について議論することさえ、恐れや非難が入り混じった目で見られてしまい、自殺をするなんて頭がどうかしているとたいていの人は考えている。
つまり、自殺は不道徳であるからということになる。だからこそこのテーマは感情論になりがちで、答えのない疑問であるのでここは賛否両論の双方の立場を慎重に考察したいとシェリーケーガン氏は言っている。
まず、考えていきたいのは、自殺についての「合理性」と「道徳性」の2点を明らかにしたい。
最初に合理的な見地から自殺の評価にとりかかるときは、自殺を考えている人にとって何が得になるか損になるかという、合理的な自己利益の問題だけに注意を向けていくことにする。
ではどんな状況ならば、自殺は合理的に決断になりうるのか。仮に死んだほうが良いという真実である時があるとしたらそれはいつであろうか。
人生がとても悲惨で、もう生きていない方がましというケースであるのだろうか。仮にそうだったとしても、自分がそうした状況下にいるという判断を信頼するのは、本人にとって合理的でありうるのだろうか?その判断に基づいて行動することは、本人にとって合理的でありうるのだろうか?答えは論ずるまでもなくノーかもしれない。それは、死んだ方がましなほど人生がひどい状況に陥った時、人は明晰な思考が出来ないと思われるからだ。現に死んだほうがましというのが正しいとありうるのかを様々な哲学者が、以下の論法で自殺について論じてきた。
今の境遇が良くなるだろう、あるいは悪くなるだろうと比較する為には、その人が既にどんな「状況」や「状態」にあるのか。
二つの状況や状態を記述して比較できなくては、そもそも比較の意味をなさない。これを「二状態要件」という。
いずれにしても通常は、何をした方が良くなるか悪くなるかの判断をするときは二状態要件を満たすことになる。例えば、これから恋人と結婚しようか、仕事を辞めようか、離婚をしようか、田舎に引っ越そうかと選択をする際に、生じるだろう二つの状態を比較してどうするのが良いのかを考える。未来が良くなるか、悪くなるかは生じる状態が二つあって比較できるからである。
しかし、自殺を考えていて、死んだほうが良いかを話し始めるとしたら、二状態要件は満たされない。
それは、状態や状況は存在の前提とするからだ。だから、次のように問う事ができる。みなさんは幸せですか?悲しいですか?退屈してますか?こうしたことは全て存在の前提とする。
死が本当に終わりならば、すなわち死んだ後に私は本当に存在しないのならば、私が死んだ後に置かれる状況や状態はないので記述しようがないのだ。それならば「私は死んだほうがまし」という判断がどうして理にかなうなどということがありうるのだろうか。
しかし「生きててよかった」がある以上「死んだほうが良かった」は否定出来ないのも事実だ。痛みと苦しみと惨めさに満ちた、ゾッとするような人生を想像してほしい。その人が人生が長く続けば続くほど人生は悪くなる。どの瞬間も拷問と苦痛でしかない100年の人生を生きるよりは、どの瞬間も拷問と苦痛でしか30年の人生を生きる方が確実に良い。
そうしたケースでは、短い人生の方が本人にとってましだ。これは3章でとりあげた快楽主義者から言わせれば「絶対的悪い死」よりもさらに悪い生になる。このようなテーマの中でシェリーケーガン氏の考えは、
今後、生きていること自体がどれほど価値を持っていても、それでも埋め合わせられないほど状況が悪くなる場合もある。
と述べている。
消耗性疾患の末期の人を想像したら今後の人生は痛みと苦しみ以外なにも残らない。
恐ろしい事に、痛みや苦しみ、無力さの合計が増す一方になる場合もある。したがって、状況が悪くなるにつれて、死んだほうがましというのが本当に当てはまる時点に到達するであろう。
少なくとも、本人が明晰に考えていて、自分の状況を客観的に評価する事ができ、その結果、生き続けたら送る事になる人生を正しく見積もれる事を前提にしている以上、自殺は理にかなっている。
とはいえ、自己利益の観点に立つなら、ある点で死んだほうが本当にましなほど人生が悪くなるケースだけだという事だ。
しかし、現代社会では、このような条件を満たさないで自ら命を投げ出す人が多いと感じる。恋人に振られた、失業した、事故に遭い、残りの人生を車椅子で過ごす事になった、邪険な離婚を経験した。
そこで以前の人生と比べり、夢見ていた人生と比べたりして、今の人生に生きる価値がないと思い込む。期待していた人生がなかったとしても、やはり存在しないよりは良いのだ。
それでは次の疑問に移りたい。それは、自殺の決断は明晰で冷静になりうるのだろうか?
この問題については痛みや苦しみ、精神的苦痛によって判断が曇っている可能性が高い点だ。実際死んだほうがましだと正しい状態にいる人なら誰もがひどい痛みや苦しみに苛まれているに違いないので、自分の状況について明晰に考えることなどとても無理だろう。だから、結局自殺が合理的な判断となることなどないように思える。もし、苦しみの中で自殺をしない事を決断したなら、今後も苦しみが続く可能性が高いであろう。
シェリーケーガン氏はこれは最も興味深い主張で、真剣に考える価値があると言っている。この考えを適切に評価するには、このように問いかける必要がある。
「自分の思考が痛みやストレスで曇ってしまう可能性がある時に下した判断を信じることは、いつも理にかなわないのだろうか?」
もしみなさんがある病気でひどい痛みに悩まされて、身体能力も著しく制限されているとしよう。だが幸いにもその症状に対して処置を施すことは可能で、ほとんどの場合その処置は成功する。成功すれば患者の痛みはなくなり、以前の生活に戻れるが、少しの可能性として失敗もあるわけだ。みなさんは手術を受けるべきか、拒むべきかどちらを選択するだろうか。想像するに誰もが手術を受けると選択するだろう。それも、リスクはほとんどなく、ほとんどの場合成功するのだから。しかし、ここで心配になる。この判断は正確なのか、信頼できるのか。自分の置かれている状況でただただストレスを抱え、痛みも強い中、そんな情緒不安定で判断したのだから本当に信頼する事ができるのか?たしかに、これほど痛みがあるのだから、どう決断するかは、二の足を踏み、考えて直すかもしれないが、感情的になっているのだから手術を受けると判断するのは合理的ではないという人が出てきたら完全に間違っている。みなさんは何らかの判断を下さなければならない。
ここで自殺の話に戻ろう。もし自殺をしない事を決めたなら、今後の苦しみは圧倒的に高くなり、生きる価値を取り戻す可能性は殆ど残っていない。逆に自殺すれば全ての苦しみが終わる。そして、苦しみがあまりにも大きので判断力は曇っている。精神的ストレスや痛みに影響されながら考え、決めなくてはならないからこそ、2度、3度考え直すほうが正しいし、医者と話し、自分を愛してくれる人に十分話し合った上での下した判断なら理にかなったものとして信頼するに値するのではないだろうか。
シェリーケーガン氏の考えは、自殺の合理性という問題に的を絞っている限り、自殺は時として正当化できるのが結論だ。
では次に自殺の道徳性に対する疑問に目を向けてみよう。原則として、自殺は合理的には選択となりうるが不道徳であることは言うまでもないであろう。現に理性は人に道徳性に従いよう求める。
自殺の道徳性に関して宗教を持ち出せば神の意思に背いている事が結論となるだろう。しかし、この問題に関しては聖書の中に答えはないように思う。神学から自殺を考えれば多くの議論がありそうだが、ここはあまり考えないようにして、次の道徳的主張に移りたい。
私たちは命を与えられていて、命はとても素晴らしいものであると指摘する。私達は感謝するべきで、与えられた贈り物を大切にして、それによって恩返しをしなくてはならない事を意味する。
つまり、私達は生き続ける義務があるとして、自殺は道徳に反すると主張する。誰に感謝するかは、誰に命を与えられたかは、親か神かと議論が分かれるところだが、親にしろ神にしろ贈り物に感謝して恩義を返すのは正しいことなのか。そもそもどうやって恩義を返すのか。恩義を返す事に同意したなら、自殺は贈り物を拒絶する事になる。万が一感謝すべきなのは自然だとしたら、この場合本当に恩義が生じうるかは明白ではないし、神が命の贈り物なら死んだほうがましな人生でも我慢して感謝して生きろと言うのだろうか。このテーマはかなり難しいが、私たちの行動は結果を通して道徳的か否かを判断されていたりもする。
自殺に最も大きな影響を与えるのは自殺する本人なのは明らかだが、愛する人や自殺の話を聞き、気にかけてくれている人にもかなりの影響がある。
何しろ通常は、誰かが自殺すると、その家族や友人に大きな嘆きや苦しみをもたらすからだ。しかし、自殺者の家族や友人に嘆きや痛みをもたらすという、自殺のネガティブな結果があるとしても、もしその自殺者にとって死んだ方が本当にましなら、そのネガティブな結果を全て考えても、なお本人を受ける恩恵の方が優るかもしれない。
さらに、死のうと思っている人を愛し、気遣う人々のことを考えているときには、愛する人の苦しみが終わりを迎えるなら、全体として実はほっとする事があるかもしれないことも心に留めておく必要がある。
もちろん、この人の選択肢が自殺をするか、何かの病気の末期が間ずっと苦しみ続けるかもしれないのであれば悲しむだろう。
しかし、選択肢は限られている。限られた選択肢も、すごく残酷で悲しい現実だが、苦しみを終わらせる方の意見に賛同するかもしれない。それならば、結果に関する限り、自殺は時として正当化出来るといえるであろう。
道徳性を考えるとき、功利主義的立場と義務論的立場を考える事ができる。功利主義とは、結果が唯一重要な事だとする道徳観である。つまり、万人の幸福を同等に扱いながら、正しいか誤りかは万人がどれだけ多くの幸福を生み出せるかが問題であるとする道徳の主義である。
義務論的立場は、結果だけでなく他の事柄も道徳的に重要だという。自分の行動の良し悪しを判断するとき、もちろん結果にも目を向けるべきだが、同様に他の事柄にも目を向ける。他の事柄とは、その結果をどうやってもたらすかにも注目を向けるという事だ。そして、特に結果を生み出すために誰かを害する必要があるかどうかが大いに重要だと義務論者は主張する。
こうした立場がある中で、シェリーケーガン氏はこのように述べている。
功利主義の立場を受け入れようと、義務論的立場を受け入れようと、これがわたしには正しいと思える結論だ。自殺は常に正当であるわけではないが、正当な場合もある。とはいえ、なおも重要な問題が残る。自殺しようとする人に出会ったらどうするべきなのか?その場合には、相手が同意原則の肝心な条件を全部満たしていると自信を持って言えるかどうか、自問するのが妥当だと思える。
自殺に関しては、かなり難しいテーマだと私は思うし、このテーマを考えることさえ批判の声があるだろう。しかし、世の中には明日にも苦しむ選択肢がない方々も存在することを知り、このテーマを考えていく必要があるのではないかとわたし自身は思っている。
まとめ



我々はいずれ死ぬ運命にある以上、この難題な「死について」のテーマを考えることは非常に価値があることであり、死について考えることで生きる意味やどう生きるべきかを深く考えされられる。
第一章では「死は何故悪いのか」について考えてきた。その事実は、これから経験する人生における良いことを全て剥奪されるからである。何故死が悪いことでありうるのかについて、まだまだ完全には答えが出ないにしろ、剥奪説こそが、進むべき正しい道なのではないだろうか。この説は、死にまつわる最悪の点を実際にはっきり捉えているように見える。しかし、その剥奪説が死が悪いことでありうる事を捉えてるとすると不死は良いことなのかという疑問が残る。
そこで第2章では「不死について考える」をテーマに述べてきた。結論は、不死は何の魅力もなく、むしろ永遠の退屈になりうると考えた。よって死は、永遠の退屈を阻止してくれる最も必要なことであるということだ。しかし、私達は時として早く死にすぎるというのが悲しい現実だと捉えてきた。
そこで、死について考えながら「人生の価値の測り方」を第3章では述べてきた。
人生には、快感と痛みが存在して、その二つを足し合わせて合計した結果がプラスであれば、生きる意味があり、マイナスなら生きる意味がないと主張する快楽主義者のことも第3章では伝えてきたが、人生は快楽と痛みだけではないと述べた。人間の人生はラットがレバーを押しただけで得られる快感とは違い、芸術に触れたり、美しい夕日を見たり、夢中になるほど面白い本を読んだり、驚くべき発見をしたりする経験から得られる快感もある。そんな快感と痛み、実績と失敗を合計した人生の価値を測る、人生の質に重要視して考える「ニュートラルな器説」の考えを持っている人や、また、人生の中身に重視するだけでなく、人生そのものに価値があるという「価値ある器説」の人の考え方なども第3章でまとめた。
最後には最も難問だと思う自殺行う上での「合理性」と「道徳性」についてまとめた。結論は、功利主義の立場を受け入れようと、義務論的立場を受け入れようと、自殺は常に正当であるわけではないが、正当な場合もあるということだ。
しかし、これから生きる上で様々な困難に出くわし心折れる事があるだろう。だが、それは一時期の悩みであって永遠ではないことも頭に入れなくてはならない。現代社会において、今この時の苦しみからの解放を求め自殺する方が増えてきている。自殺は、時として正当な場合もあるが、それは極めて例外である。ここまで死について考えることは普段の日常では考えられないであろう。しかし、死に対しての理解を深めると生きる価値を見出し、どのように生きるべきなのかが見えてくる。この文章を読み終えたみなさんも今後も死に対しての考え知り、生きる意味を深めてもらいたいと思う。





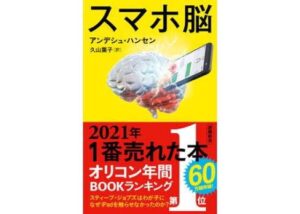







コメント